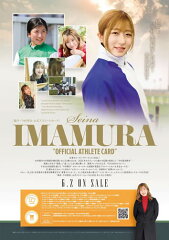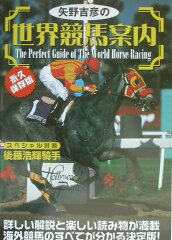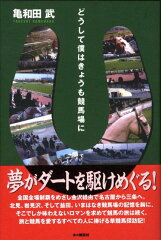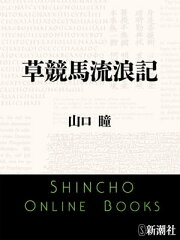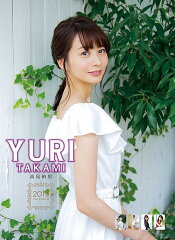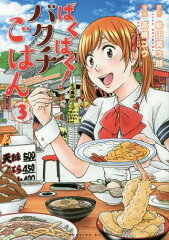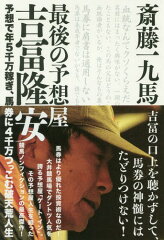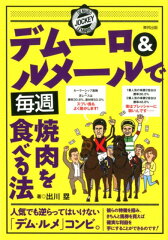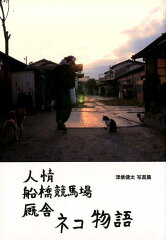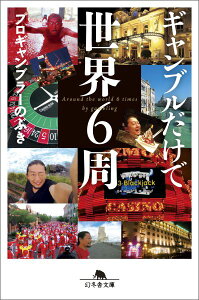日本国内、海外の競馬場の訪問記です。こんなことしてていいのかなあ。でもやめられない。
そこに競馬があるから > クランジ競馬場 > クランジ競馬場 その5 ~シンガポール競馬の歴史など~

クランジ競馬場のウィーナーズサークル
*クランジ競馬場レポートのつづきです。
初めからお読みになる方はクランジレポートその1からどうぞ。
どうも。荷桁です。どうもバタバタしており牛歩になりがちなのですが、ブログの更新を進めてまいりましょう。
さて。今回もクランジ競馬場レポートでございます。前回のレポートではシンガポールという国についていろいろご紹介をいたしました。シンガポールと言う土地とその歴史をある程度知っていただいたら、お次はシンガポールの競馬の歴史を、ということで、今回の記事ではクランジ競馬場だけでなく、シンガポールの競馬の歴史について、ざっくり書いておくこととします。
既に申し上げました通り、シンガポール競馬はその長い歴史に終止符が打たれてしまった訳ですが、どんな感じで当地で競馬文化が育まれていったのかという部分につきまして、遺構や痕跡なども含めて、ゆるゆるとご紹介していければと思います...

さて、そんな訳で、シンガポールの競馬の歴史である。
シンガポールの競馬の歴史をブログで書くにあたっては一応、ちゃんとした資料にあたったので、まずはそちらをご紹介しておこう。まずは『Singapore racecourse, 1842-2000』という本で、シンガポール国立図書館で閲覧した書物だ。この本はその名の通り、シンガポールの競馬の変遷などについて、歴史的な部分も踏まえて簡潔に紹介してくれているぞ。

もう一冊、これもシンガポール国立図書館で閲覧した『The winning connection : 150 years of racing in Singapore』という本。こちらの本は過去の大レースの勝ち馬や、会場の様子などへの言及が多く、当時の雰囲気や社会的な背景を知るのに参考になった。ちなみにこちらの本の筆者はSumiko Tanさんというようで、調べたところ、シンガポール生まれのと中国と日本にルーツに持つ女性だそうだ。
とりあえず、これからざっくりご紹介する、シンガポール競馬の歴史はこれら2つの書物に書いてあることをそれっぽくまとめてあるものだと思ってくれたまへ。
シンガポール競馬の歴史が始まったのは1842 年のこと。シンガポールの歴史を振り返ると、東インド会社のラッフルズがシンガポールに上陸したのが1819年。正式にイギリスの植民地になったのが1824年。海峡植民地の首都となったのが1832年と考えると、だいたい、イギリス人はこの地にやってきて20年ちょいで「そろそろここでも競馬やるか」となったイメージである。オーストラリアはクック上陸が1770年で、初の競馬が1810年という感じなので、まあ、イギリス人っつーのはだいたい新しい土地を発見してからそのくらい経つと競馬をやりたくなる性質を持ってるということなのだろう。
1842年にシンガポールで「競馬やろうぜ」と言い出したのは、ウィリアム・ヘンリー・マクロード・リードというスコットランド人の若い商人で、こいつを中心に、まず「シンガポール・スポーティングクラブ」という組織が立ちあがり、競馬場建設の準備が進んだようである。彼らは競馬場を整えてシンガポール最初の競馬を開催することを目指して政府に定期的な競馬開催のための土地を要求し、めでたく、土地と開発許可をもらうことに成功し、クラブを立ち上げてから約半年後の1843年2月に彼らは最初の競馬を開催することになる。
ちなみに、シンガポール・スポーティングクラブは「スポーティングクラブ」を名乗っているだけあって、競馬だけでなく、社交のためのゴルフやクリケットなどスポーツ全般を扱う団体のようなイメージだったと思っておいてくだされ。
さて。そんな流れでシンガポール・スポーティングクラブによって、最初に競馬場が作られたのは現在のファーラーパークという場所であった。それもあって、シンガポール最初の競馬場はファーラーパーク競馬場と呼ばれることが多いのだが、厳密にはこの競馬場ができてすぐファーラーパーク競馬場と呼ばれた訳ではなく、この競馬場が後に移転する際、その跡地を公園化するときに当時の市委員の会長の名前から「ファーラーパーク」と名付けられたという経緯のため、リアルタイムではファーラーパーク競馬場と呼ぶ人はいなかったという点に注意が必要だ。
ファーラーパークは今も、同名の地下鉄駅などがあるので、まあだいたいどの辺のエリアかというのはすぐに分かるだろう。現在のリトルインディアのちょっと西側あたりにあったようなイメージだ。


ちなみに、現在もリトルインディアからファーラーパークのあたりをうろついていると、「Race Course Road」「Race Course Lane」など、この地に競馬場があったことを匂わせる地名がちらほら見られるぞ。
さて。そんなこんなで始まったシンガポール競馬は、最初の内は植民地支配をしていたイギリス人とマレーの王族のみで楽しんでいた内輪の社交イベントだったが、徐々に中華系の富裕層の皆さんがクラブにスポンサーや馬主として加わるようになり、だんだんと規模を拡大していったようである。
イギリス本国の競馬がそうであったように、実際に競馬を開催したり馬を出走させたりというのはあくまで一部の支配層や富裕層であったが、シンガポールにおいて、競馬は早くから植民地住民の重要な娯楽イベントとして位置付けられていたようで、年数回の競馬開催日は仕事はもちろん、学校でさえ半日の休みが与えられていたとのこと。また競馬イベントにはシンガポール総督も積極的に出席していたようだ。
植民地省政府はシンガポール・スポーティングクラブに低い賃料で土地を提供する一方で、公共の競馬場としてふさわしい状態に管理維持することをクラブに求めていたといい、シンガポールの競馬場はけっこう早い段階から独立志向というより、政府とずぶずぶというか、よろしくやっていくような感じで発展してきたようである。まあ、競馬が事実上、シンガポールの支配層・富裕層がほぼ全員一堂に会する社交の場として機能していたことを考えれば、そんなもんか、という感じである。
同じ時期に、同じくイギリス領・海峡植民地であったマレー半島のクアラルンプール、ペナン、イポーにも競馬場が開設されていたようで、これらの競馬場とシンガポールの競馬場を統括するため、1896年には海峡競馬協会(the Straits Racing Association)が設立されている。後にこの団体はマラヤン・レーシング・アソシエーション(MRA)と名前を変えて、この団体は今もマレー半島の競馬の統括団体となっているぞ。
そんなこんなで順調に発展していたシンガポール競馬だが、1914年から1918年にかけての第一次世界大戦中にはオーストラリアからの馬の輸入が滞り、レースの開催も制限されるなどあったようだ。ただ、植民地政府と仲が良いシンガポール・スポーティングクラブは戦時下でも競馬を開催し続け、政府に多額の寄付をおこない、戦時資金の調達に貢献したとのことである。明確な記述は見つけられなかったが、まあ、競馬が有事の際にも存在意義を発揮したと言うのはクラブの立ち位置を考える上でも大きかったと思われる。
ここまでの歴史を読んでいただくと、なんとなく1842年にウィリアムのあんちゃんをきっかけに立ち上がったシンガポール競馬は、その初期段階から競馬場の土地の提供や、社会的位置づけも含めて、植民地政府の支配層の意向に沿いつつ、うまいこと発展を遂げてきたという部分がイメージできるかと思う。政府とよろしくやってきた、というのは逆に言えば政府にそっぽ向かれると途端に厳しくなるということで、それが顕在化したのが2023年の突如の廃止宣言ということになろう。まあ、ただでさえ土地が少ないシンガポールという土地柄、その狭い国土で競馬なんてものをやるために、まとまった土地を融通してもらおうと思うと、どうしても政府に助けてもらわないといけないというのはあるだろうし、何とも言えないところですわな。
さて、そんな流れででシンガポール競馬は発展し、さらには他の海峡植民地の競馬場との連携も始まり、いい感じになってきた。1924年にはシンガポール・スポーティングクラブはスポーツをいろいろやりましょう団体ではなく、より競馬に特化した団体になっていくんだということで、シンガポール・ターフクラブと名前を変更しているぞ。
競馬開催が盛り上がってくると、さすがにほぼ都心にあるファーラーパークの競馬場では手狭になってきて、開発が進んできた周辺環境を鑑みても、さすがにここで競馬をやりつづけるのは限界だと言う雰囲気になり、1933年、競馬場はファーラーパークから、ブキティマという都市近郊部に移転をすることになる。先ほどもちらっと、申し上げた通り、古い競馬場の敷地は、1919年から31年にかけて市委員の会長を務めたローランド・ジョン・ファーラーさんにちなんで、1935年にファーラーパークと改名されて、現在に至っている。
そんなわけで、シンガポール競馬の次なる舞台になったのはブキティマの地だ。
ブキティマはファーラーパークから西へ6キロほどいったところにあるエリアで、当時は自然が多い保養地的なイメージで、現在も自然保護区が広がり、周辺には住宅や高級マンションがある閑静なエリアという感じだ。マップで上から見ると、わりと分かりやすくここに競馬場があったんだなというシルエットが確認できるぞ(執筆時)。

旧ブキティマ競馬場近くには、「Turf Club Road」という通りが現在も残っている。ちなみに、ちょっと正確にいつからという記載が見つけられなかったが、シンガポール・ターフクラブはブキティマ移転後にブキティマ・ターフクラブと名前を変えて活動してしていたようだ(その後クランジ移転で再びシンガポール・ターフクラブに戻る)。
そんなブキティマの競馬場は1933年にオープン。もともとはゴム園の一部だった土地とのことで、当時の通貨で300万ドル以上が競馬場の建設費用に費やされたそうだ。300万ドルが現在の通貨価値でどのくらいかというのはめんどくさくて調べていないが、まあ、すごかったのであろう(適当)。オープン時には盛大な式典が催され、当時のシンガポール総督、サー・セシル・クレメンティが競馬場のオープンを宣言したとのことだ。ブキティマ競馬場は当時アジアの英領にあったボンベイ、ラングーン、クアラルンプールなどの他場を参考に作られており、かなり豪華なコースとスタンドだったようで、当時の新聞は「間違いなく東洋で最高の競馬場の1つ」と新競馬場のことを評していたようだ。
当時の記録によるとブキティマ競馬場のグランドスタンドは3層構造でエレベーターも完備されており、座席はすべて籐張りで非常に快適だったようだ。賭けはすべて4ドル単位のトータリゼータで行われていて、会員以外は賭けることができなかったようだが会員は24000人を数えていたようで、けっこうな規模感だったことが想像できる。白人系、マレー系、中華系、さらには19世紀後半から増えてきた日系住民なんかも競馬場に集っていたようで、まあ華やかだったようだ。シンガポール国立博物館の展示なんかを見ていても、この20世紀前半の日本に占領されるまでの間は、文化的にもかなり充実していた時期とされているようで、イギリス統治下における”シンガポールの一番良い時期”に競馬文化も発展した、というイメージになるのだろう。
だがその後、1941年に日本がシンガポールを占領すると状況は一変する。日本軍はシンガポールでの競馬開催を禁止。ブキティマ競馬場のスタンドと周辺の建物は医療施設に転換され、厩舎エリアも軍用車両の駐車場として使用されることになってしまった。さらに記録によると、コース内のフィールドには、パパイヤ、バナナ、タピオカといった作物が植えられ、ほとんどの競走馬は安楽死させられ、いい馬は日本に持っていかれたとのことらしい。
一方で同じ日本統治下のマレー半島ではペナン、イポー、クアラルンプールでの競馬の継続が許可されていたようで、シンガポール競馬だけがかなり厳しい対処をされたかのように感じられる。だが、これはもともとシンガポールは食料の輸入をオーストラリアやインドからのルートに頼っていたところ、戦争の激化と日本占領の流れでそれがストップし、けっこうシャレにならないレベルの食糧不足に陥っていたこと、さらには日本軍による占領後も外からは連合国の反撃に遭うわ、内側では抗日華僑と呼ばれる中国系住民の反発が強かったことから、さすがに日本としてもシンガポールでは競馬を開催してる場合じゃねえ、ということでこうなったと見るのが妥当であろう。
今でこそ日本人や日系企業も多いシンガポールだが、日本統治時代はそれまでのイギリス統治時代がわりと安定していたことや抗日華僑の弾圧で虐殺された犠牲者が多く出たこともあって黒歴史となっており、競馬もその影響を大きく受けていたのである。
1945年、第二次世界大戦が終結し、日本占領時代が終わってしばらくすると、ブキティマ競馬場は接収から解除され、クラブは再びこの競馬場を復活させるべく、復旧作業を開始。約2年後の1947年11月に再び競馬開催が再開することになった。
その後は、戦後の復興、1965年のシンガポール独立などを経て、シンガポールの経済的発展とともに、シンガポール競馬も国民的娯楽としての地位を高めていく。独立前の1960年にはこれまでクラブ会員メンバーと馬主のみが入場を許可されていたスタンドに、一般人が5ドルの入場料で入ることができるようになり、その後は多くの国と同じように、競馬の大衆化により馬券売り上げが増えていき、それにより競馬産業を発展させていくシステムでシンガポール競馬も動いて行くこととなる。
ブキティマ競馬場も一般入場客の増加に伴い、施設やスタンドを拡張。1973年にはコンピューター式のトータリゼータシステムが導入され、1981年にはスタンド(ノース・グランドスタンド)が増設、1982年には大型ターフビジョンを導入など、世界でもかなり先進的な競馬運営がシンガポールでは行われていたと言ってよいだろう。
そんなこんなでブキティマの地でシンガポール競馬は隆盛を極めるが、1990年代になってくると、またファーラーパークのときと同じように、だんだんブキティマ競馬場も手狭になってきたのであった。
このへんからは荷桁の私見も混じるのだが、今でこそブキティマ競馬場近くには地下鉄も走っているが、当時はそんなものもなく、競馬開催時には渋滞もすごかったであろうことが想像できるし、周辺も宅地開発が進んでいって国際レースをできるような大ぶりなコースに拡張しようと思ってもなかなか難しい状況が起こっていたのだろう。ブキティマは先述の通りもともと保養地的な場所で、白人系に人気の高級住宅街だったこともあって、周辺地価もシンガポールの中でもかなり高めのエリア。仮に周辺の土地を購入して競馬場の敷地を拡張しようと思うととんでもないお金がかかったのであろうと想像される。
また、他の見方で、単純に資産価値が高いブキティマ競馬場の敷地に目を付けた政府が、同地の再開発のため、クラブへ郊外への移転を迫ったという説もある。ちょっと極端な例えだが、日本で言うと目黒競馬場がバブルくらいまで残っていたようなイメージなので、まあ敷地的な拡張性もないし、政府も再開発したそうな感じだし、郊外に移転するのが最適解かもね、という感じの結論になったのだろう。
そんなこともあって、結果的にクラブはブキティマからの競馬場移転を決断することになるのである・・・。移転の先は、クランジ。ここでようやくシンガポール競馬はクランジの地までやってくることになるのである。

ちなみに、ブキティマ競馬場の跡地には2023年まで、開催当時のスタンドがそのまま残っていて、商業施設として利用されていた。奥がもともとのグランドスタンドで、手前が増設されたスタンドと思われる。
結局、クランジに移転後も、ブキティマ競馬場跡地は再開発らしい再開発はされなかったんかい・・・という意見はさておき、この施設についてはまたちょっとどこかで触れようと思っているので、ここではこんなもんにしておこう。
さあ、そんなこんなで長くなってきたが、いよいよクランジ競馬場である。クランジ競馬場への建設工事が始まったのが1995年。オープンは1999年で、実に4年もの歳月をかけて完成したのがこのクランジ競馬場だ。
ブキティマ競馬場から移転した、クランジ競馬場はシンガポール北西部の郊外エリアにあたるが、MRT(シンガポールの地下鉄的なモノ)の駅直結、高速道路のインター至近と、アクセスは抜群で、シンガポールのどこからでも不便なく行ける場所に立地していた。

なおかつ郊外と言うことで、広大な敷地に、国際レースをするにも十分な、立派なコースとスタンドを備えたシンガポールの競馬の集大成とも言える競馬場となった。さらにはナイター設備も備えて、ナイター開催ができるようになり、これも日中の気温が高い熱帯のシンガポールでは商業面からも画期的なことであった。
シンガポール・ターフクラブがクランジ競馬場への移転に打って出た背景には、シンガポール競馬の国際化の促進という狙いがあったようで、クランジ競馬場のオープンを記念してアジア競馬会議もシンガポールで開かれている。当時のシンガポール競馬の流れを見ても1998年、ブキティマ競馬場最後の年に、伝統のシンガポールゴールドカップがシンガポールで初の国際競走となり、翌年のクランジ移転以降はクリスフライヤー国際スプリントとシンガポール航空国際カップの2つの国際レースが新設され、その後も年々、多くの重賞が国際競走となっていった流れがあった。
日本人にもなじみ深いのが、こちらのシンガポール航空国際カップであろう。2006年には日本調教馬のコスモバルク、翌年にはシャドウゲイトが勝利するなど、日本のホースマンたちにも海外挑戦の舞台としてシンガポール競馬に目が向いてきたのであった。
そんな流れで、クランジ競馬場移転以降、シンガポール競馬はますます発展していく。最盛期は移転から10年くらい経過した2010年頃で、この頃の売り上げは毎年のように10億シンガポールドル(約1,050億円)を超え、所属馬は1,500頭前後にのぼっていた。だいたい同じ時期の大井競馬場の売り上げが年間1000億程度だったので、シンガポールの人口規模でそのくらいの売上を叩き出していたということになる。
ところが、シンガポールの競馬はそこから急激に暗転していくことになる。以降のシンガポール競馬没落の歴史は冒頭の資料には記載がないため、ここからはJAIRのウェブサイトに全文翻訳が掲載されたレーシングポストの以下の記事を参考にしながらその流れを説明して行くことにしよう。
参考:https://www.jairs.jp/contents/w_news/2023/7/1.html
シンガポール競馬衰退の大きなきっかけになったのは同国でのカジノの解禁である。シンガポールでは2005年にカジノ解禁が宣言され2006年には「カジノ規制法」による法整備が行われ、2010年からカジノを含めた統合型リゾートが本格オープンになった。競馬客がカジノに奪われたというのは勿論あるにはあるのだが、政府は観光産業としてのカジノを解禁する一方で、国民へのギャンブル依存症対策も同時に強化しており、そのへんがシンガポール競馬にダメージを与えた構図になったと考えられている。このへんはちょっと話が複雑なので、詳しく見ていくことにしよう。
もともとシンガポールでは「賭博法(Betting Act 1960)」と「普通賭博場法(Common Gaming Houses Act 1961)」という法律があり、そこでギャンブル規制がされていたのだが、それはリアルでの賭場開帳を念頭に置いた違法ギャンブルを取り締まる趣旨の法律で、競馬は当然例外的に合法とされていたので、まったくその影響は受けていなかった。
だが、シンガポールでは時代とともに上記の「賭博法」と「普通賭博場法」の間隙を突いた違法オンライン賭博が蔓延し、これが庶民の間で人気を博していったのだ。具体的にはオンラインカジノや海外サイトのスポーツベッティングのようなもので、当時の法律ではこのへんに関する具体的な規制の条項がなかったので、シンガポール国外のサービスや国外にサーバーがあったりするものだと、わりとやりたい放題だったのである。
これらの違法オンライン賭博が野放しになっていただけでなく、この「オンライン賭博に関する規制条項がない」という状態が最悪だったのが「シンガポール・ターフクラブによる馬券のオンライン発売」についても、当時の法律では合法とも違法とも規定されていなかったため、シンガポール・ターフクラブがオンラインで馬券を売ったとすると政府から「それは違法です」と言われてつぶされる可能性があり、身動きが取れなくなったのである。
そんな状態だったので、違法賭博がインターネットやスマホの普及でバンバン蔓延してくる間も、シンガポール・ターフクラブはネット投票システムの構築に投資することができておらず、従来型の本場開催と場外発売の売上に頼る経営を続けざるを得なかったため、オンラインベットの市場では違法賭博に完全にしてやられているという、ちょっと日本では考えづらい状況が生まれていたのだ。
この状況下で、前述のとおり2005年にシンガポールでカジノ解禁が宣言され2010年からは実際にカジノの営業が始まることになるのだが、このカジノ解禁はどちらかというと外国人観光客マネーを集めることでの産業振興を念頭に置いており、自国民がこれによりギャンブル依存症になることは政府としても防ぎたい流れであった。というわけでカジノ解禁が法整備された2006年以降、シンガポール国内でのギャンブル依存症対策が強化され、新たに広告規制などが導入されるようになるのだ。すなわち競馬は、カジノのとばっちりのような形で売り上げを増やすためのプロモーション活動をガチガチに制限されてしまったのである。
つまりシンガポール競馬は最盛期を迎えた2010年頃には、
・カジノに客を奪われる
・宣伝や広告を規制されて新規顧客が獲得しづらくなっている
・オンラインで馬券も売れず、違法オンライン賭博にボコボコにやられている
という踏んだり蹴ったりの状態になっていたのである。
ようやく政府も2015年に「遠隔ギャンブル法」という法律を制定し、違法オンライン賭博を規制すると同時に、例外的に認められた組織による馬券のネット販売を合法と定めたのだが、それでも事態はまったく好転しなかった。馬券のネット販売は合法になったものの、もともとはオンラインギャンブルをガチガチに規制する法律だったため、馬券のネット発売についてもいろいろと規制が入った状態での合法化になってしまったのである。具体で言うと、Singapore Pools といった政府が認可した事業者以外はオンライン馬券の販売がNGとなっていたのである。
では、シンガポール・ターフクラブもさっさと認可を取ればよかったじゃないか、という意見もあろうが、規制当局はギャンブル依存症対策やマネーロンダリング防止などの観点から、オンラインギャンブルは基本的に広めたくないという姿勢があり、認可基準はかなり厳しいものになっていたようである。結果として、シンガポールターフクラブは、認可を得るためのシステム構築や運営体制の整備に苦慮し、結果として競馬の胴元にもかかわらずオンラインでの馬券販売の認可をなかなか得ることができなかったというなんともトホホな状態になっていたのだ。
加えて、ギャンブルをしなかった層に対するイメージアップのための広告宣伝もできなかったため、競馬人気はダダ下がり。昔からのファンに来てもらう本場開催・場外発売依存の状態が続き、売り上げはどんどん落ちていったのであった。2015年には、かつてあれほど頑張って増やしていた、国際競走もほとんどが廃止されてしまう。入場者数も2010年に1日平均1万1,000人だったのが、コロナ前の2019年には6,000人と10年でほぼ半減してしまうのだ。
ここまで聞いていて「いやいや、シンガポール・ターフクラブはもっと政府にいろいろ働きかけないとアカンやろ」と思った人も多いであろうが、そういうことにならなかったのにもちゃんと理由がある。ご存知のとおり、独立後のシンガポールはリー=クアンユーが指導する人民行動党が事実上の一党独裁で絶対的な権力を持っていた。土地の融通に端を発して、もともと歴史的に政府とよろしくやっていたターフクラブもご多聞に漏れず、独裁政権に非常に従順な組織となってしまっていたのだ。クラブの幹部は政府から派遣された競馬運営のことなんてよく分からない役人のような連中で占められていてしまい、オンライン馬券を合法化してくれ、うちもネット馬券発売OK事業者として認可してくれ、宣伝活動を認めてくれといったロビー活動などの手が打てず、まさに自滅していったのだった。独裁政権から派遣されている人材が競馬産業発展のためにわざわざ勇気を出して政権に意見するメリットなどまったくない訳で、これはもう構造的な問題であった(かつて廃止になったいくつかの日本の地方競馬場と同じですね)。
2019年、シンガポール・ターフクラブは自ら馬券をオンラインで売ることを諦め、認可事業者であるSingapore Poolsに馬券販売をすべて委託することで、コスト削減とオンライン馬券発売の拡大を狙ったのだが、そこに襲い掛かったのがコロナ禍であった。日本をはじめ、他国の競馬がコロナのおかげでオンライン売り上げが爆上がりしているのに対し、シンガポールではシステム整備が遅々として進んでいなかったこともあり、その恩恵に預かることができず、とうとうシンガポール政府は2023年、住宅用地確保を理由に、競馬を廃止すると発表するに至ったのである。
参考として挙げた記事によるとコロナ禍からすぐの2021年頃には政府の中で内々に廃止が決定されていたとの噂もあり、実質、政府の意向により潰されたというのが本当のところであろう。
かくしてクランジ競馬場は2024年10月5日の開催をもって、閉鎖。2027年には競馬場の土地は政府に返還され、シンガポール・ターフクラブも実質解散ということになる見込みで、ここにシンガポール競馬の歴史は完全に終了することになるのである。
さて。そんなわけで、ダラダラと述べてまいりましたが、こちらが、シンガポールの歴史のざっくりした概要である。
まあ、いろいろ述べましたが、とりあえず、
・シンガポール競馬はイギリス植民地時代から続いていた伝統あるものであった
・都心のファーラーパーク、近郊のブキティマ、郊外のクランジと移転をしてきた
・日本占領下と最後の10年程以外は比較的順調に成長してきており、シンガポールの文化・政治に貢献してきた
・ただ、政府と近すぎたことが仇となって自滅した
といったあたりを押さえていただければよいかと思います。
ひとまず、ここらで予備知識的な情報はひと段落し、次回からは実際にクランジ競馬場に向かうレポートをスタートできればと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします・・・。


>>クランジ競馬場レポートその4へ
*この競馬場が好きな方はこちらの競馬場もお好きだと思われます。
セランゴール競馬場 その1~いざマレーシア競馬~
ペナン競馬場 その1 ~再びマレーシア競馬へ~
フートー競馬場 その1 〜さらにベトナム競馬へ〜
フレミントン競馬場 その1 ~メルボルンカップ事始~
ムーニーバレー競馬場 その1 ~オーストラリア競馬~
カイントン競馬場 その1 ~もうひとつのカップ・デー~
ガルフストリームパーク競馬場 その1 〜アメリカ競馬事始〜
ポンパノパーク競馬場 その1 ~アメリカのハーネスレース~
フェアグラウンズ競馬場 その1 〜ニューオーリンズに競馬しにきた〜
ルイジアナダウンズ競馬場 その1 〜競馬旅行の運の尽き〜
マルサ競馬場 その1 〜いざ地中海競馬へ〜
ニコシア競馬場 その1 ~空路キプロスへ~
笠松競馬場 その1 ~名馬・名手の里~
浦和競馬場 その1 〜南浦和からバスでアクセス〜
*クランジ競馬場に関する記事は以下にもあります。
クランジ競馬場 その1 ~いきなりお詫び~
クランジ競馬場 その2 ~クランジ馬券奮闘記?~
PR
ブログ内検索
カテゴリー
最新記事
(01/01)
(01/01)
(11/30)
(10/22)
(08/15)
プロフィール
HN:
荷桁勇矢
性別:
男性
職業:
若隠居
趣味:
逃げ
このブログについて
このブログは「そこに競馬があるから」といいます。
競馬場巡りに魅せられてしまった筆者、荷桁勇矢(にげた ゆうや)が、日本の競馬場、海外の競馬場を訪れながらその様子をご紹介して行くブログです。
紹介している競馬場の情報は訪問当時のものですので、競馬場に行かれる際は最新の情報をご確認のうえ、自己責任で行っていただきますようお願いいたします。
またこのサイトの写真や文章は基本的に無断で使用されると困るのですが、もしどうしてもという方は荷桁までご連絡ください。そのほかご指摘やご質問がある方も荷桁まで直接ご連絡ください。コメント欄は管理が面倒そうなので当分オープンにはしないつもりです。悪しからず。
連絡先:
nigetayuyaあっとgmail.com
ツイッター:
https://twitter.com/YuyaNigeta
note:
https://note.mu/nigetayuya/
Flickr:
http://www.flickr.com/photos/nigeta/
競馬本紹介ブログ始めました。
荷桁勇矢の競馬本ガイド
競馬場巡りに魅せられてしまった筆者、荷桁勇矢(にげた ゆうや)が、日本の競馬場、海外の競馬場を訪れながらその様子をご紹介して行くブログです。
紹介している競馬場の情報は訪問当時のものですので、競馬場に行かれる際は最新の情報をご確認のうえ、自己責任で行っていただきますようお願いいたします。
またこのサイトの写真や文章は基本的に無断で使用されると困るのですが、もしどうしてもという方は荷桁までご連絡ください。そのほかご指摘やご質問がある方も荷桁まで直接ご連絡ください。コメント欄は管理が面倒そうなので当分オープンにはしないつもりです。悪しからず。
連絡先:
nigetayuyaあっとgmail.com
ツイッター:
https://twitter.com/YuyaNigeta
note:
https://note.mu/nigetayuya/
Flickr:
http://www.flickr.com/photos/nigeta/
競馬本紹介ブログ始めました。
荷桁勇矢の競馬本ガイド